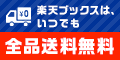幸福とは?
なんのために生きているのか?
何を目標としているのか?
そう悩んでいる人は多いはずです。
この本は、著者が自身の人生を通して、その答えの一端を見つけ出し、紹介しているものです。
紆余曲折の激しい、賑やかで、壮絶な人生を歩んできた著者が、
実体験を元に、そのときどきで感じたことを自身の成功、失敗談を交えながら展開される自叙伝です。
同じような悩みを抱えている人が、解決の糸口をここから見つけ出せればいいなと思っています。
著者紹介
中田敦彦
1982年生まれ。
2003年、慶應義塾大学在学中に藤森慎吾とオリエンタルラジオを結成。
2004年にリズムネタ「武勇伝」でM-1グランプリ準決勝に進出して話題をさらい、ブレイク。
2014年には音楽ユニット「RADIO FISH」を結成し、2016年には楽曲「PERFECT HUMAN」が爆発的ヒット、NHK紅白歌合戦にも出場。
2018年にはオンラインサロン「PROGRESS」を開設。
2019年からはYouTubeチャンネル「中田敦彦のYouTube大学」の配信をスタート。
著書概要
第一刷発行 2020年8月31日
260ページ
発行社 株式会社徳間書店
コンセプト
夢が叶おうが、そうでなかろうがそれに至るプロセスを重要視すること
対象読者
幸せとは何か悩んでいる人
二番目に手を挙げる
SNSの発達により、誰でも簡単に情報を発信できるようになりました。
数え切れないほど多くの人が発信していく中で成功した人は、どのようなプロセスを経て成功したのでしょうか?
全く前例のない場所で成功した人はごくわずかです。
多くの人は、二番目に手をあげて成功しました。
別名をアーリーアダプターともいいます。
著者は、ゼロイチで新しいものを生み出す人よりも、二番目にやってくる人というポジションが向いているため、その長所を最大限に活用しました。
「RADIO FISH」というダンスミュージックグループを結成し、一世を風靡しました。
あの「PERFECT HUMAN」で有名なあれです。
あのパフォーマンス集団は、その業界の先駆者であるEXILEファミリーを参考にして作り上げたものだったと著者は語ります。
ただこれは、著者がその道のトップになろうとして始めたものではありませんでした。
その目標をただやるために始めたプロジェクトだったそうです。
このコンセプトでも示した通り、著者は、目標を達成することでなく、その目標を達成するために何をするかに重きを置いています。
夢へ向かう道のりをどう楽しむか。
目標を達成してしまうと、いっときの達成感を感じることはできます。
しかし、その後は深い焦燥感と悲壮感が待ち受けています。

ここでポイントとして、
その目標までの道のりがあまりにも遠いものは途中で熱が冷めてしまう
ことを挙げています。
手の届きそうな目標や夢を事細かく設定することが大切で、継続するポイントであると著者は語ります。
著者は受験勉強で、薄い参考書を何冊もやり切る勉強法をしていたそうです。
これも手の届きそうな目標を達成していく一つの手法です。
ここで運営者の体験談を話します。
運営者も著者同様に、勉強するときに具体的な小さい目標を設定するようにしています。
一時期、英語の勉強(TOEIC TOEFL)をしていたことがあります。
初学者の運営者にとっては途方もなく難しいものだと感じました。
しかし、こまめに(二ヶ月間隔程度で)受験するようにし、
この回までには何点取得したい、
それを達成するためには一ヶ月後までにはどのくらいのレベルまで持っていかなければならない、
ならば今日この勉強をどれだけしよう、と事細かに計画が立てていました。
これをするには、自分の学習能力を十分に把握しておく必要があります。
その小さな積み重ねをゲーム感覚でクリアしていき、最終的には900点超えを達成することができました。
ただ、不足の事態(急な友人からの遊びの誘いなど)で、計画通りいかない時もあると思います。
そういう時は、その不測の用事で縮小する勉強時間を、用事の前後で調節すれば良いと考えています。
勉強が習慣化してくると、今日はあんまり捗らなかったなと焦りが出てくるはずです。
人間を動かす大きな要因は、焦り、危機感だと思います。
それらを持つには、面倒な作業を習慣化しなければなりません。
習慣化するまで継続する方法として、著者の方法は有効であると思いました。
安住を恐れろ
現在のコロナ禍で生活が大きく変化しました。
それ以前でも、テクノロジーの進化によって大きな変化を感じ続けてきました。
この状態がずっと続くとは限らない。
変化しないものは時代の変化についていけなくなり、消滅します。
コロナで生活が一変して、著者が運営するオンラインサロンも打撃を受けました。
会費を払えないサロンメンバーからの要望により、月額5980円から月額980円まで下げたそうです。
時代の変化に合わせて仕組みや立場を変化させ、対応することが生き残る秘訣であると著者は語ります。
コロナの影響を強く受けたのは飲食業界です。
それは事業の自由度が低いことが理由であると考えます。
飲食店は、ほとんどが実際に足を運んでもらうことが前提なので、外出制限でその前提が満たされなくなりました。
そうすると収益は急激に下がり、次々と店をたたむ事態となってしまいました。
別の書評でも述べましたが、事業を多様化させておくというのは、リスクを軽減させるという点で非常に重要なことであると考えます。
今日が安定しているからといって、明日も同じように安定しているとは限りません。

多少の毒は大事
皆さんは、人間関係を構築することは得意ですか?
人と会話することが得意で、好んでいる人もいると思いますが、運営者は苦手です。
この毒というのは人間関係での煩わしいことを意味しています。
著者は、元来一人でいることがあまり好きではなく、たくさんの人と交流していたい人間だと語っています。
関わった分だけ面倒なことも起きますが、その毒が案外大事なのではないかというのが著者の考えです。
それは、互いに毒を吐き出したり、摂取していないと面白い経験に巡り会えないからです。
著者が単独の露出が多くなっている中で、お笑いコンビを組んでいたり、「RADIOFISH」のようにグループとして活動しているのはそのような理由が根底にありました。
運営者はあまり人間関係を築くのが得意ではないと、我ながら感じています。
連絡を取ったり、会話をすると一般的な人が受け取る以上のものを感じ取ってしまうからです。
細かい相手の表情や、言動までも気にしてしまうので疲労が溜まります。
ただ、そこから得られることもあるのだと著者の考えから学びました。
言葉の重要性
言葉に触れない日はありません。
町を歩いていても、看板などで自然と目や、耳に入ってきます。
さまざまな浮き沈みを経験した著者が生き残れた要因として復元力を挙げています。
人気が低迷したときにも、現状を分析、それに対応し、自らを復元してきた著者ですが、
そこで重要だったのは、言葉だったと語ります。
それが顕著なのが、現在著者の活動の中で最も広く知れ渡っているコンテンツであるYouTubeチャンネルです。
「武勇伝」などの活躍を知らない世代は、著者がよく喋る面白い先生であると認識しているかもしれません。
運営者も動画を見たことがあり、スピーディで必要なことをわかりやすく解説している動画たちは心地が良く、どれも興味をそそられるコンテンツばかりです。
卓越した言語スキルと、解説内容への深い理解により完成度の高い作品を作りあげている著者の作品をぜひ見ていただきたいです。
終わりに
幸福=夢を叶えると考えている人もいるとは思います。
しかし、この本を通して、夢を叶えようと必死にもがいている自分こそが一番幸せなのではという考えを持ちました。
「夢を叶えるために自分がやったことを紹介します」という広告がありますが、
それはその人が成功したやり方であって、万人に共通して当てはまるものだとは限りません。
そのやり方も一つの手段であると頭の片隅に置いておいて、いろんなことを試しながら
自分だけのやり方を探すその過程を楽しんだもの勝ちなのではないでしょうか。
ぜひ、手に取っていただきたい一冊です。